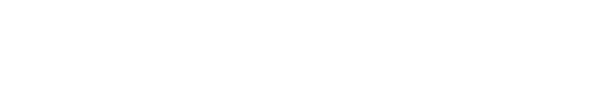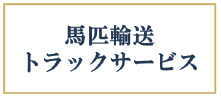KAWASAKI
2021年春に開校した、校舎です。
川崎駅より徒歩10分のところにある沢山の動物達が居る学校です。ワシミミズクや、ヤギ、マイクロブタさんなどを飼育しております。
神奈川県内、の方が多く通われております。板橋校開校の時から、期待されていた川崎校舎です!
静岡本校から、お引越ししてきて、専用のお部屋を作ってもらえたケヅメリクガメのつよし君がいつも元気にお散歩しております。
様々な動物達の繁殖にチャレンジしており、少人数制ではありますが、一番学籍確保が難しい校舎です。
中高部
中等部では、自分らしさを大切に動物と関わり、ふれあいながら学習していきます。
「あいさつ」「すなお」「思いやり」「良いところを伸ばす」「できない事をあきらめない」といったしっかり学んでいかなくてはならない、ところをゆっくり自分のペースで向上心や、自己肯定感を持ちながら学んでいきます。
当校だけでなく、在籍中学校の先生とも連携しながら、サポートして行きます。
最後まであきらめずに取り組み、将来の夢や希望をもって楽しい、学びの多い学校生活を作っております。
高等部
全日制高校卒業資格と同じ高卒資格を取得できます!
飼育の実習は、専科の生徒と一緒に行います。講師や先輩から教えてもらいながらできることからはじめて行きましょう。学校へ通えない方は在宅で学ぶことからスタートできます。入校すると、まずは履修科目を決めるところから始めます。必須科目以外に選択科目もあるので興味のある科目を選びましょう。
転・編入学生は不足している科目の単位分を履修します。
高等部では動物関連のライセンス・資格の取得が可能です。
※なお、高卒資格はスクーリングやプリント提出、テストなどを受け、指定単位を取得した者にかぎり取得できます。
本校はあくまでも加盟校(サポート校)のため、鹿島学園の基準をクリアしなければ高校3年間の在籍で卒業することはできません。ただし、転入や編入の場合は前校で取得した単位を持ち越し、足りない分の単位のみを鹿島学園で取得することになります。個人個人で必要な学習量や取得しなければならない単位数、在籍しなければいけない期間などが異なります。
本校では、期日までにレポートなどを提出させたり、テストを行わせたり、また、鹿島学園にそれらのレポートを提出したりと、卒業までの管理や処理をしっかりと行い全面的にサポートします。
-
学びのスタイルは自分で決める
通信制高校とは、レポートの提出(添削指導)と、月2回程度のスクーリング(面接指導)で学ぶシステムです。好きなときに勉強する「自学自習」が基本ですから、自分流の学び方でムリなく高卒資格を取得できます。
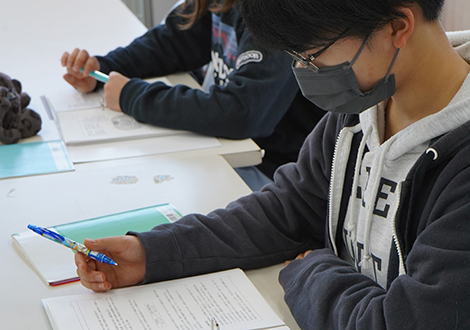
-
卒業までの道のりをきめ細かくサポート
教師が、どの科目をどのようなスケジュールで履修すればよいか、一人ひとりにあったベストな履修方法をアドバイス。 学習面だけでなく、卒業後の進路のことなども気軽に相談してください。

-
進学希望者に対する受験指導も充実
進学希望者のための受験指導も行います。
時間に余裕のある通信制高校ならではの受験対策を、きめ細かくサポート。試験対策だけでなく論文や、面接指導も個別で行います。難関私立大学や、専門学校への進学を実現させます。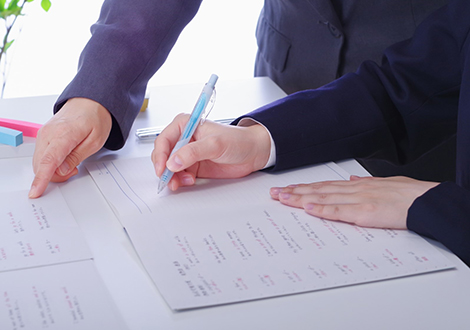
-
自分の予定にあわせてスクーリング
年2回~3回程度のスクーリングは、完全予約制となっており、自分の都合にあわせた日程を立てることができます。また、放送視聴やレポート課題の提出を、スクーリングの出席時間に振り替えることもできます。

動物飼育を中心に学び、週に1回高等学校のレポート作成を行います
カリキュラム例
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 【10:00〜12:00】 |
実技 | 実技 | 実技 | 実技 | レポート |
| 午後 【13:00〜16:00】 |
実技 | 実技 | 実技 | 学科 | レポート |
※実技・学科は、天候や研修により変更の場合がございます。
高等学校の
レポート提出とは…
週に1回鹿島学園高等学校の教科書・プリントをもとに高等学校卒業に必要な単位を取得するためのレポートを作成します。
専門部
動物飼育技術学院では、動物の飼育員や、動物関係のお仕事を目指している高校を卒業した後の進路として専門部もあります。
実際に動物にたくさんふれ、学習することが多く、気づきや発見の機会がたくさんあるのが特徴です。
日々細かく動物たちの飼育管理について学び個体について理解していきましょう。
校外学習の時間では、移動動物園や、動物園実習など、積極的に参加し、動物関係の仕事について、どんな社会貢献ができるか、また動物が好きな人や、苦手な人にどの様に紹介したりすれば動物と人と距離が縮まるのかを考え将来の仕事のために経験を積んでいきましょう。
失敗しても今は学んでいる最中です。失敗を次に活かせるように学び、楽しい学校生活にしていきましょう。
動物ふれあい学級
動物ふれあい飼育学級では、同年代の生徒さんと一緒に飼育に取り組むことが難しい、個別にサポートをしてほしいなど、様々なお悩みがある方にお勧めなコースです。
個別にサポートが必要な部分について承ります。
Q1.
小学校からほとんど学校にいけていません。中学校生活が心配です。
A1.
動物に少しでも興味がある。お子様自身が学校以外であれば外にでて活動ができる状況であれば、ぜひ資料請求の上ご見学ください。週1回からでも、土曜日や日曜日など通常授業がない曜日でも、可能な限り、ご対応しております。
Q2.
学習障害があります。受け入れは可能でしょうか?
A2.
大丈夫です。1回でわからないことも、何度も経験しましょう!大好きな動物のことです。時間がかかってもきちんと最後までやることが大切です。
Q3.
高校への進学に自信がありません。長期間不登校だったので勉強や集団行動両立が自信ないです。
A3.
不登校が長く続いてしまうと、学校の勉強に中々ついていけていない状況ですので、ご心配かと思います。心の負担を考えて、動物飼育技術学院へ入学したあとに、高等部の方を始める方法もございます。高校の新入学については、4月・10月とございます。
集団行動に慣れてから、高校の勉強についても取り組んでいくことで、一歩ずつできることを増やしていくこともできます。
Q4.
現在中学にも通えず、外にもほとんど出られない状況です。好きな動物の動画は毎日みています。
A4.
ご本人に当校のパンフレットを見せていただき、ご提案ください。動物の飼育の学校です。動物を飼育することに興味があるようでしたら、ぜひご見学ください。見学の際に話すことができなくてもかまいません。まず、今まで行くことができなかった学校との違いを感じてください。好きなことから一歩前へ踏み出すための学校です。
様々なご事情はあるかと思います。できる限り力になりたいと思いますので、まずは資料請求、お電話にてご相談ください。




動物飼育技術学院 川崎校
〒210-0003 神奈川県川崎市川崎区堀之内町10-18
TEL:0120-777-044